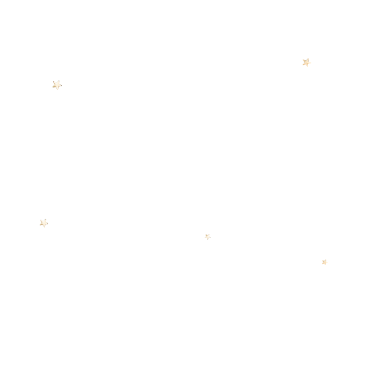CONCEPT MOVIE
コンセプトムービー
EVENT
イベント情報

女性の心とからだの健康についてゲストと一緒に考えよう
『わたしたちのヘルシー ~心とからだの話をはじめよう i n Mar. 2025』開催決定!
「正しい知識を身につけて、自分の心やからだに向き合いながら過ごしていけるように」という思いを込めて毎年開催しているこのイベント。
今年は「女性の健康週間」(3月1日~8日)と「国際女性デー」(3月8日)に向けて3月7日より配信します。専門家の先生がよく質問されるリアル相談などをもとに、女性の心とからだのヘルスケアについてさまざまな角度から考える授業形式のオンラインイベントです。
女性の心とからだの健康に寄り添う医療ヘルスケアの専門家と、「わたしたちのヘルシー」の趣旨に賛同する著名人が登場。ここでしか視聴できないスペシャルなトークセッションから視聴者のお悩みに役立つ情報をお届けします。
みなさまのご参加をお待ちしています。
FEATURED ARTICLES
ピックアップ記事
NEWS
お知らせ
VOICE
応援メッセージ

アナウンサー
谷岡慎一


フリーアナウンサー・タレント
阿部華也子


ウィメンズ・ヘルス・アクション共同代表、東京大学医学部附属病院副院長、日本産科婦人科学会副理事長
大須賀穣


アイドル
和田彩花


浜松町ハマサイトクリニック特別顧問、東京女子医大病院産婦人科非常勤講師、グランドハイメディック倶楽部倶楽部ドクター
吉形玲美


TikTokクリエイター・タレント
景井ひな


ウィメンズ・ヘルス・アクション共同代表、一般財団法人日本女性財団 理事長、NPO法人女性医療ネットワーク 理事
対馬ルリ子


アナウンサー
島田彩夏


藤沢女性のクリニックもんま院長
門間美佳


看護師モデル
東あさか